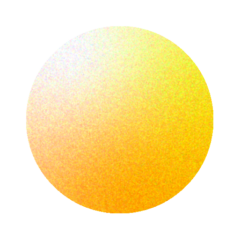それは、わたしの思い出のミニチュアを集めたものだけど、箱庭のように静かに置いておかれるものではない。記憶のエッセンスを携えながら、わたしを中心に回っている衛星だ。
○*
遠くの星に引っ越すことにした。もともと宇宙船で生まれて、たくさんの星を渡ってきた。地に足のついた暮らしを続けていると、足や羽根が衰える気がして、どこへも行けなくなるんじゃないかと怖くなる。移住地からの定期的な脱出と、それからの無重力の日々を手配すると、ひどく安心したものだった。
急に連絡が取れなくなったら嫌だろうなと思って、地球の何人かには引っ越すことを伝えた。本当に好きでずっと一緒にいたけれど、私の気まぐれで、大きな意味で疎ましく思ってしまった人たち。今まで地球から出たことがないからという理由で友人Fが中継地点の惑星までついてきてくれた。
中継惑星は殺伐とした岩地で、かろうじて均された停車場には大小さまざまな宇宙船が休んでいた。隅っこには星間バスや貨物宇宙船のドライバーたちが憩う古びたダイナーがあった。時間があったので中に入って飲み物を頼んだ。
実は、Fがこのまま着いてきてくれるかもとほんの少しだけ期待していたので、地球行きの星間バスのチケットを取り出して眺め始めたときはがっかりした。がっかりして、むかついて、つい意地悪を口に出してしまった。
「あなたは地球が世界の中心だと思ってるから、離れようとはしないのね。」
Fは困ったような顔をしだけど、こちらを伺いながらはっきりと言った。
「それは君が宇宙船生まれだから、いろんなところに旅をするのがいいと思っているんでしょう。正直言うと、僕は地球から離れる君のことはよくわからない。」
「わたしから見たらわたしが中心だよ。地球が離れるの。」
地球に居続けることが不安な気持ちはわからないんだろうな。最後だと思うと、ずっと皮肉っぽく思っていたことがポロポロと次いで出てきた。
「少し文化が繊細なだけで自分たちが一番だと思って。わたしのこと、野蛮な異星人だと思ってたんでしょう。地球人なんて大嫌い。」
地球で居心地が悪かったとき、嫌なことがあったときに、恨みのように浮かんでいた言葉を口に出した。本当に伝えたかったのは簡素な寂しさだったはずなのに。
しばらく黙った後にFが口を開いた。
「映画も、ラーメンも嫌い?」
大きなスクリーンで物語を見る。エンドロールが終わると、秘密結社のように同じ場所で物語を共有した人間が散り散りに劇場から出て行く光景が好きだった。真夜中にラーメンを食べに遠出をした。どこの星にもない変てこな食べ物だと思ったけど、なぜか美味しくて好きだった。
どちらも、Fが教えてくれたことだった。
「好きだよ。」
あなたのことも。泣きそうなのがばれないように、伝票に目を落として言う。
どうかフラットに聴こえていますように。
「君と行く映画もラーメンも当たりが多かったからなあ。」
彼はのんびりと言って席を立った。
ぐるぐるとこの気持ちをどうしようか考えていたらターミナルについてしまった。しょうがなくわたしたちは最後の挨拶っぽく言葉を交わし始めた。
「こんなところまで送ってきてくれてありがとう。」
「これあげる。 僕の読みかけだけど。」
一冊の本。持っていた本は引っ越し準備の段階ですべて電子化したので、墨だまりがある字が既に懐かしかった。
「読んだことないけど、君の好きな作家だね。」
「うん、いい本だから。」
地球での持ち物はいる・いらないを決めるのが面倒ですべて処分していたので、手元には宇宙旅行が終わったらこれもまた処分されるであろう必需品しかなかった。まさか物を持って星をまたぐことになるとは。
「わたしの引越し先の数センチ分が地球由来の空間になるんだね。」
Fは悪戯っぽく笑う。
「本の侵略だね。」
柔らかい物言いで物騒な言葉を言うので笑ってしまった。地球の情報を湛えた一冊の本がぽつんとある星を想像する。記憶の拠り所を物として持てるイメージは、意外にも心強かった。
「いろんなことを教えてくれてありがとう。あなたのことを忘れても、この本は繰り返して読むと思う。」
でも、この人にはもう会えないんだと、これから離れる億光年の距離に、気が遠くなり泣きそうになる。また会いたいくらいならむしろ忘れてしまった方が楽だろうか。
彼は静かに明るい声で言った。
「僕のこと忘れないで、たまにメールしてよ。百年先までドメインとっておくからさ。」
「墓標のようなアドレスになるね。」
なぜかFの墓石に掘られたメールアドレスを想像した。
彼は言った。
「君の格好や動きもいいなと思うから寂しいけど、僕は君の話す言葉がいちばん好きなんだから。」
Fも何かが無くなる気持ちになっているんだろうか。
「じゃあ着いたら連絡するね。」
「気長に待ってます。」
「百年?」
「百年。君は友達だから死ぬ直前にメッセージが来ても喜んで返信する。僕ができなかったら子か、孫か、ルンバに返信させる。」
「悪いけど、ルンバは三百年前から掃除しかできない。」
「いまだに掃除もできないときがあるけど。」
最後のくだらないやり取り。ずっと覚えていても、綺麗に忘れてしまっても、どちらもよいことだと思った。
ふたりは搭乗口の手前でじゃあね、と手を振って別れた。
本当のところ、実体を持たないテキストメッセージは私が動くよりも速く、三日もあれば地球に着くだろう。昔見たSF 映画のようにタイムラグが大きくなりはしないけど、お互いのわからないことが多くなっていくのは簡単に想像できた。
人生で異星の知人を気にかける余裕はあまりないだろう。どんどん変わっていく。形も思考も見る影も無くなるかもしれないのはお互い様だ。
それでも彼が今ここにいる私に手を振るために、冗談でも死ぬまで友達だと伝えてくれることが嬉しかった。
顔を上げると、地球で見るよりずいぶん大きな衛星が、空にきらきらと浮かんでいた。